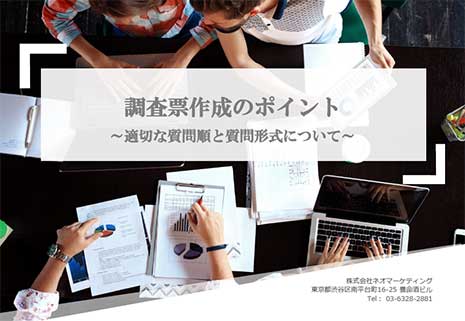顧客満足度調査
Customer SatisfactionAbout顧客満足度調査とは
顧客満足度調査(CS調査)とは、商品を購入したり、サービスを利用したお客様が、
商品・サービスによって「想定していた満足が得られたかどうか」を把握する調査です。
「期待」よりも「評価」が高くなれば「顧客満足度」は高くなります。
顧客満足度調査は、「Customer Satisfaction(カスタマーサティスファクション)」略してCS調査とも呼ばれます。
目的によって、アンケート調査とインタビュー調査を使い分けますが、ネットリサーチによるアンケート調査が一般的です。
顧客満足度調査のメリット
顧客満足度調査をアンケート調査で実施することで、商品サービスに対する顧客の満足度合いや推奨度合いを数字で可視化できます。
また、不満度合いや不満点の具体的な内容を記述してもらえることも可能です。
定期的に数値を比較することで、顧客評価を経年で定量的に評価することが可能です。
インタビュー調査で実施することで、商品サービスのロイヤルユーザーがリピートに至るまでの心理的変化、理由を確認することができ、既存ユーザーのロイヤルティを高めるヒントにつながります。
満足度や推奨度についての、より定性的な現状把握と改善のヒントが得られることがメリットです。
ネオマーケティングの顧客満足度調査の特徴
-
01.アンケート会員数が多く、調査対象者を確保できる
日本国内アンケート会員2700万人(提携含む)から、ご希望の調査対象条件に合致する対象者に調査を行ないます。
どのくらいのサンプルサイズが確保できるか、お見積りも可能です。調査が困難だと思われる対象者条件であっても、まずは一度ご相談ください。 -
02.適切な調査設計が可能 インタビューを通じたインサイトの特定も得意
調査設計、分析、提言を専門に行うリサーチャーが多数在籍し、課題を解決する調査設計をご提案しています。
また、潜在ニーズの把握、インサイト発見を専門とするリサーチャーも在籍しているため、インタビュー調査を通して、顧客満足度の理由や背景を深堀して理解を深めることも可能です。 -
03.顧客満足度調査の20年以上の支援実績と、様々な業界傾向をふまえた提案
年間2000件以上の調査実績と、様々な業種での支援実績があります。そこで培ってきたノウハウを基に、最善のご提案をいたします。
-
04.満足度や推奨度を把握した後の、改善施策まで提案可能
顧客満足度調査は、満足度を確認した後の改善施策を検討することが本来の調査目的です。
カスタマーサクセスサービスについて
ネオマーケティングではリサーチだけでなく、その後の施策実行までを支援しています。
顧客満足度調査の調査項目例
調査項目はその商品・サービスによって、またどのように分析するかによって異なりますが、ここでは代表的な項目例を紹介します。
満足度は5段階(満足、まあ満足、どちらともいえない、やや不満、不満 など)で取ることが基本です。
-
回答者属性
満足度の結果を分析するために、回答者がどのような人なのか、取得します。
-
個別項目の満足度
商品サービスの個別の項目について、それぞれ満足度を取得し、強みと弱みを明らかにします。
-
総合満足度
商品サービスについて、全体的な満足度を取得します。
-
NPS(ネットプロモータースコア)
NPSは商品サービスを人にお勧めしたいか、「非常にそう思う」の10点から「まったく思わない」の0点までの11段階で回答してもらう質問です。10点または9点をつけた人は「推奨者」、7〜8点が「中立者」、6点以下を「批判者」と分類します。
-
NRS(ネットリピータースコア)
顧客の継続可能性を取得する質問です。「1年後この商品(サービス)を継続して使いたいと思いますか?」という質問に対して、「積極的に継続したい」「今と同じ程度継続したい」「その時になってみないとわからない」「できれば継続したくない」「絶対継続したくない」の5段階で取得します。
分析・アウトプットイメージ
CSポートフォリオ分析
「CSポートフォリオ分析」とは、項目別「満足度」と「総合満足度」から、重点改善要素を抽出します。問題を改善するアプローチのための分析手法です。
満足度を構成する各要素毎の満足度を縦軸、総合満足度と各要素毎の相関係数(関連の強さ)を横軸にとり、各要素を付置して重点的に改善する要素を明らかにし、改善施策に優先順位を付ける判断材料とします。
1. 最優先改善項目
総合満足度への影響度も高いのにも関わらず、満足度が低いゾーン。
このゾーンの項目が総合満足度を引き上げていくうえで最優先に考慮すべき、要改善検討項目となる。
2. 現在の満足度の源泉
現状満足度も高く、総合満足度への影響も高いゾーン。
現時点での満足度の源泉とみなすことができる。
3. 現状維持項目
各項目の満足度は高いものの、総合満足度への影響は低いゾーン。
とりあえずは現状を維持しておけばよい項目と言える。
4. 最低評価項目
各項目の満足度も低く、総合満足度への影響も低いゾーン。
経年比較
顧客満足度調査を定期的に実施することで、経年での比較が可能です。
前回調査と比較して、どの項目がどのように変化したかを分析することで、どの施策、商品改良がユーザーに評価されているのか、効果検証を行なうことが可能です。
Q&Aよくあるご質問
NPSは顧客ロイヤルティの指標として一般的ですが、人によって点数の定義が異なること、日本人の場合極端な点数を付けない傾向があること、という点には留意が必要です。NPSを活用する場合は、10点または9点をつけた「推奨者」に重点的に注目することを推奨しています。
様々な顧客をひとまとめに考えて満足度を見るのではなく、顧客を幾つかの階層に分類した方が、より詳細に商品・サービスの立ち位置を知ることができます。その指標となるのが、NRS(ネットリピータースコア)です。
NRSを活用した顧客満足度調査については、こちらのコラムをご覧ください。
CS調査(カスタマーサティスファクション)からCS(カスタマーステイタス)調査へ、NPS×NRSへ
一概には言えませんが、ある企業様では5段階評価のtop2で70%以上を満足者と捉えたりしています。重要なのはカテゴリやブランドや商品によって異なるため、自社で独自の指標(ノルム値)を創ることです。
調査項目をどのように設計するか、調査結果をどのように分析して活用までつなげるかのノウハウがあることが一番のメリットです。自社で実施する場合は、特に調査結果を適切に分析するができず、ただ毎年実施しているだけ、という企業様もいます。ネオマーケティングの場合は、更に分析からどのような施策を実施すべきか、その実行部分まで支援できることが特徴です。
また、第三者機関として介入することで、忖度のない意見の聴取が可能です。
Download Listノウハウ資料ダウンロード
Related Services関連サービス
Contact
まずは、お気軽にお問い合わせください。